日本発祥の「指差呼称」は世界的に注目される手法となっています。この効果的な安全確認方法は安全標語を組み合わせることで、現場の安全意識を高め、ミスを防ぐ効果が格段にアップします。本記事では、指差呼称の基本・実践方法・成功事例を紹介します。
指差呼称の基本と効果
指差呼称とは?
指差呼称とは、「指を差し、声に出して確認する」ことで注意力を向上させる手法です。これは日本の鉄道業界で生まれ、現在では製造業や物流業など多くの業界で活用されています。英語圏では “Pointing and Calling” として知られ、日本の安全管理手法として注目されています。この方法は、複数の感覚を使うことで、作業者の注意力と集中力を高め、ヒューマンエラーを防ぐ効果があります。
✅指差呼称の基本的な手順
1.対象を指差す(ポイントは対象と指を一致させる)
2.対象の名称を声に出す
3.対象の状態を確認し、声に出す
4.「ヨシ!」と声に出す
✅ 「3つの効果:確認ミス防止・集中力向上・習慣化」
→ 指差呼称を導入することで、作業ミスを最大85%削減できることが報告されています。
指差呼称の具体的な効果
指差呼称には、単なるチェックリストでは得られない効果があります。
🔹 視覚・聴覚・触覚を活用する
→ 実際に指を差し、声を出すことで脳が刺激され、ミスを減らせる。
🔹 ルーチンワークのリスク回避
→ 繰り返し作業の慣れによる確認ミスを防ぐ。
安全標語を活用した指差呼称の実践方法
指差呼称に安全標語を組み合わせるメリット
安全標語と指差呼称を組み合わせることで、安全標語の定着率が向上することが報告されています。単なる「指差し確認」ではなく、安全標語を加えることで、より効果的な意識付けができます。
✅ 「指差しヨシ! 確認ヨシ! 命を守るヨシ!」
→ シンプルなフレーズにすることで、覚えやすく実践しやすい。
✅ 「見るだけチェックは危険のもと、指差し呼称で安全確保」
→ 見るだけで済ませる習慣を改善する効果がある。
実践のステップ
① 作業前の指差呼称リストを作成
→ 重要な確認ポイントをピックアップし、安全標語を組み込む。
② チーム全員で標語を統一
→ 例:「機械停止!OK!作業開始!」のように、決まったフレーズを使う。
③ 定期的に見直し、習慣化
→ 3ヶ月ごとに振り返りを行い、効果を検証。
ゼロ災害達成企業の安全活動事例
製造業の指差呼称
✅ トヨタ自動車が指差呼称を積極的に導入しています。彼らは “Point and Call” システムを採用し、作業者が重要なチェックポイントを指差しながら声に出して確認することで、安全性と品質の向上を実現しています。
医療分野の指差呼称
✅ ある病院では、「確認は指差し、声出して、患者安全」という標語を用いて、与薬時の確認ミスを大幅に減少させることに成功しています。
まとめ
ゼロ災害を目指すため、指差呼称と安全標語の組み合わせは効果的です。
✅ 指差呼称はミスを防ぐ重要な技術
✅ 安全標語を組み合わせることで、実践しやすくなる
✅ 各職場の特性に合わせてカスタマイズ
毎日の作業に指差呼称と安全標語を取り入れ、継続的な取り組みと定期的な見直しにより、ゼロ災害を目指しましょう!

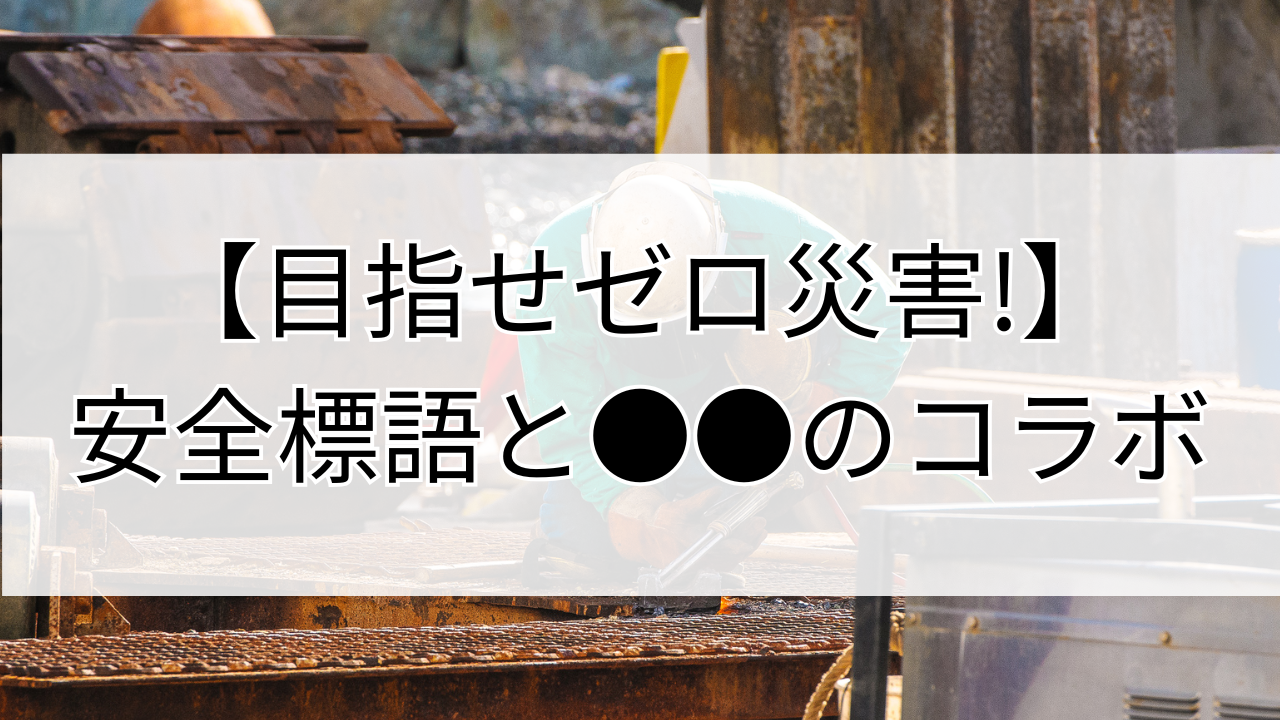
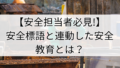
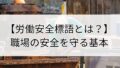
コメント