「問題が起きた…でも、何が原因かわからない」
そんなときに頼れるのが「根本原因分析(RCA)」。
今回は、**実際にどう進めるの?どこから手をつけるの?**という疑問を解消すべく、3つのステップに分けて分かりやすく紹介します💡
製造業・建設・サービス業、どの業界にも役立つ手法です!
🛠 ステップ1|問題の明確化と情報収集
まずは「何が問題か?」をハッキリさせるところからスタート。
あいまいなままだと、分析も対策もズレてしまいます。
ここでは、現場の状況や関係者の声を正確に集めることがポイントです。
📋効果的な情報収集のポイント
- 写真・動画・ログなど、客観的な証拠を記録
- 作業手順・点検記録・日報などの過去データも確認
- 同じトラブルが過去にも起きていないかをチェック
たとえば工場での装置停止トラブルでは、停止直前の操作ログや、センサーの履歴が有力な手がかりになります。
🔗 参考:NIOSH(米国労働安全衛生研究所)”Accident Investigation Resources” https://www.cdc.gov/niosh/
🎤関係者へのインタビューの方法
関係者へのヒアリングは、ただ聞くだけではダメ!
以下のコツを押さえることで、有効な情報が得られます。
- 「何が起きたか」ではなく、「どう感じたか」「なぜそうしたか」を聞く
- 責任追及ではなく、事実を探る姿勢で
- メモや録音を取り、曖昧な表現は具体化する
たとえば「いつも通りやったのに失敗した」と言われたら、「“いつも通り”ってどのような手順?」と深掘りしましょう。
🔎 ステップ2|原因特定と分析
情報が集まったら、いよいよ分析フェーズ。
ここで大切なのは、「なぜ起きたのか?」を深堀りすること。
ただし、感覚に頼らず、構造的な原因を探る視点がカギになります。
🧠なぜなぜ分析の進め方
「なぜ?」を5回繰り返す「5Why分析」は、シンプルで初心者にも使いやすい手法。
【例:段ボールが濡れて破損】
- なぜ破損した? → 濡れていた
- なぜ濡れた? → 雨の中で搬送された
- なぜ雨でも屋根がなかった? → 台車が一時的に外に出た
- なぜルートが屋外を通る? → 倉庫の通路設計に問題
- なぜ設計に反映されなかった? → 現場の声が届いていなかった
➡️ 改善点は「現場フィードバックの仕組み」にもあるとわかる!
📊データを活用した根本原因の見える化
感覚だけではなく、数値やグラフで“見える化”することも重要です。
- 故障履歴を時系列グラフにする
- トラブルの発生頻度をヒートマップで整理
- 作業者ごとの作業手順を比較して違いを分析
これにより、直感では気づけないパターンや傾向が浮かび上がります。
最近ではBIツールやExcelでも簡単に可視化できるようになっており、RCAとの相性も抜群です。
🔗 参考:Root Cause Analysis Tools – American Society for Quality (ASQ) https://asq.org/quality-resources/root-cause-analysis
🚀 ステップ3|対策の策定と実行
原因が見えたら、次は「どうやって再発を防ぐか?」です。
ここでポイントになるのは、実行可能かつ持続可能な対策を考えること。
💡効果的な対策案の立て方
- チェックリストや標準作業手順書の見直し
- 自動化・デジタル化で人のミスを防ぐ
- 教育・研修制度の改善
対策は「人を変える」よりも「仕組みを変える」ことが効果的です。
例えば、「ミス防止のため注意喚起する」より、「間違えられない設計に変える」方が実効性が高いです。
🔁実施後のフォローアップと評価方法
改善策を実行したら、「それで終わり」ではありません!
- ✅ 変化前後の数値比較(例:ミス件数、稼働率)
- ✅ 定期的な現場レビューやアンケート
- ✅ 関係者とのフィードバック共有会
改善後の追跡を怠ると、対策が絵に描いた餅になりがち。
“やりっぱなし”を防ぐフォローアップの仕組みづくりが、継続的な改善につながります。
🧠まとめ|原因を掘り下げれば、未来はもっと安全になる!
RCAは、トラブルを「ただ直す」のではなく、「もう二度と起こさない」ための強力な手法。
問題の見える化、原因の深掘り、改善策の実行と評価――この流れを押さえるだけで、あなたの職場も大きく変わります。
✅「感覚」ではなく「構造」で考える
✅ チームで協力して進める
✅ 成果を定量的にチェックする
事故やトラブルは、防げる時代へ。あなたの“なぜ?”が、未来を変える力になります!
📚合わせて読みたい!
🔹 [RCAとは?初心者にもやさしく解説した基本記事]
🔹 [5Why分析のテンプレートと活用法]
🔹 [現場で使えるヒューマンエラー対策集]

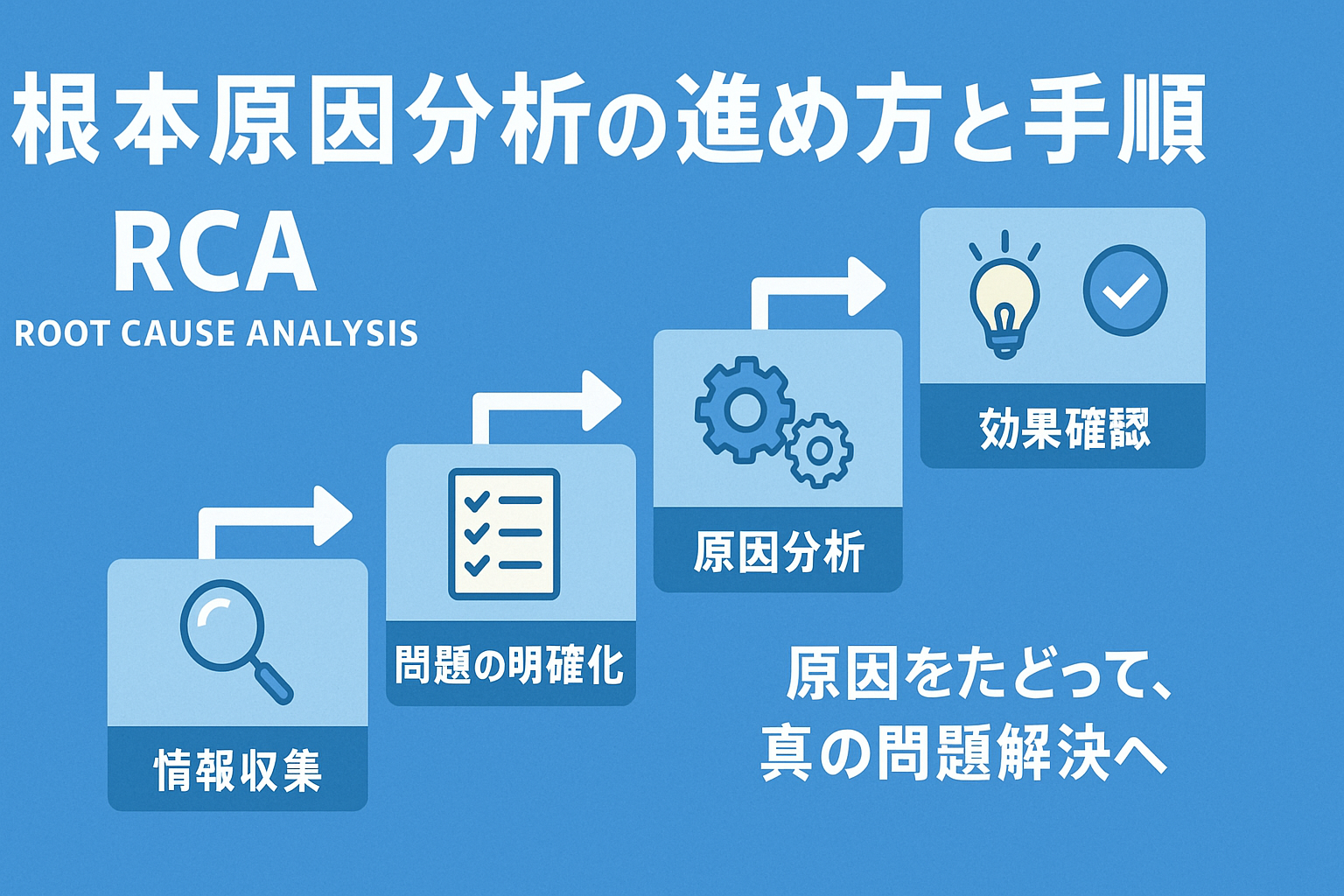


コメント